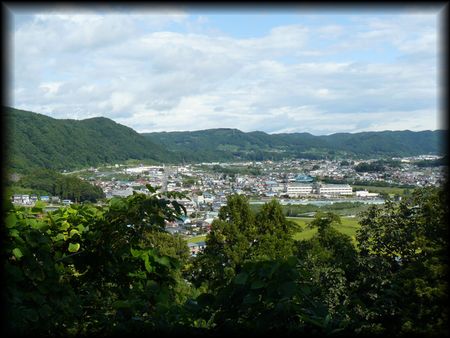|
三戸町(歴史)概要: 三戸町は中世南部氏の支配下だった地域で、鎌倉時代初期の文治5年(1189)、鎌倉政権と奥州藤原氏との間で行われた奥州合戦で源頼朝に随行した南部三郎光行が恩賞により糠部郡を賜り、建久2年(1191)に現在の南部町に入部したと伝えられています。
当初は南部町にある聖寿寺館が居城でしたが天文8年(1538)、家臣の放火により城が焼失し、変わって天文年間(1532〜55)に三戸城を大規模に改修し居城としました(元々の三戸城は鎌倉時代中期に築城されたと伝えられています)。
以降、三戸南部氏として領内を掌握し天正18年(1590)の小田原の役で豊臣秀吉に謁見したことで領土が安堵され近世大名として確立します。天正19年(1591)には一族である九戸氏との対立から俗に言う"九戸の乱"が勃発し当初は九戸氏が優勢に立ちましたが、三戸南部氏は秀吉に助力を頼み、蒲生、浅野、石田の軍に東北諸侯が加わり総勢6万5千の兵で九戸城を取り囲んだとも云われ鎮圧されています。
三戸南部氏は関が原の合戦で東軍側に付き領土が安堵され南部藩を立藩、この地が領内から見ると北側に片寄っていたこともあり寛永10年(1634)居城を盛岡城に移します。
一国一城令が発令されると三戸城は廃城とされましたがこの地の重要性は変わらず城の麓に代官所を設け、周辺地域の中心地として機能し、城も建物など施設は失ったものの掃除や石垣の修復が随時行われいざという時の為に管理されていました。
又、三戸町は奥州街道の宿場町としても整備され多くの旅人や物資の流通の拠点として経済的にも発展しました。
|